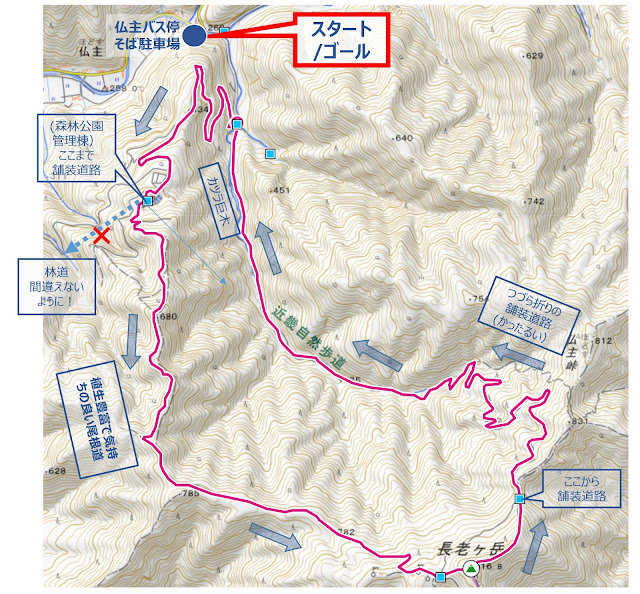昨年訪れた小塩山のカタクリの花がきれいだったので、今年も行ってみることにします。
昨年のルートは老ノ坂から大枝山、大暑山を越えて小塩山に登るルートでしたが、今年は南側の金蔵寺から登るルートを行ってみます。
このルートは大原野神社の駐車場に車を停め、初めに川沿いにある落ち着いた集落をのんびり歩いたあと金蔵寺にお参りして、見晴らし台で東山36峰の全容を眺めたあと、環境保全された気持ちの良い森の中を登ります。
小塩山頂上にある淳和天皇陵をお参りしたら、カタクリの群生地でカタクリ三昧を楽しみ、最短距離で大原野神社に戻ります。
全体を通して累積標高700m、距離5キロ、ゆっくり歩いて5時間のコースでした。
大原野神社の駐車場は広くなり自動式に変わっていました。
そこからすぐにある花の寺で有名な正法寺に行きます。藤が咲いています。
去年も見ましたが、八重桜と二重の塔のコンビネーション。去年より一週間遅めなので去年より満開です。八重桜はソメイヨシノよりも1~2週間開花時期が遅い。
ツルニチソウ。
シャガ。
民家に咲いていた鮮やかな紅い花はトキワマンサク。枝先に花が咲くのが特徴で、樹木全体が花で覆われているように見えます。
石作町の集落。立派な家も多く、川沿いの落ち着いた町並みです。
川底に野草の群生が。コンクリートの川底なのによくここまで大きく育ちました。水がきれいなのでしょう。
金蔵寺へ向かいます。
この密集している白い花はイベリス。スペイン原産の花だそうですが、自生しています。先ほど川底にあった花もおそらくイベリスかと思われます。
ここから金蔵寺への登山道。金蔵寺へのつづら折りの車道を直線で突っ切るように登って行きます。
気持ちの良い自然歩道。
途中、御堂がありますが、その横にひっそりと美少年の墓が佇んでいます。
調べてみると、桂海という名の比叡山の律師(僧のこと)が、三井寺の稚児、梅若丸と同性愛関係になったが、比叡山と三井寺がライバル関係にあったため、愛はかなわず、律師は東山に籠り、梅若丸は入水自殺を遂げたという。
悲劇の美少年、梅若丸の名は謡曲の主人公となりましたが、こちらのストーリーは、京都北白川の稚児、梅若丸が人買い商人にさらわれて東国に売られ、墨田川で亡くなったという悲しいお話。
中世当時、僧侶と稚児の間の禁断の恋を描いた「稚児物語」といわれる小説ジャンルが流行していたそうです。
ヨーロッパでもカトリック神父が少年に性行為をしたかどで大きな社会問題になっていましたが、中世においては愛の一つの形として受け入れられていたのでしょうか。
(東京都墨田区の木母寺ホームページより)
ここから金蔵寺へ登って行きます。「愛宕大権現」と書いてあるのは、明治時代の廃仏毀釈の際、愛宕山で廃棄されそうになっていた権現さまの勝軍地蔵(しょうぐんじぞう)を金蔵寺に移したことを示しています。
金蔵寺に続くイロハモミジのトンネル。紅葉シーズンは人気のようですが、新緑のイロハモミジも紅葉に負けず劣らず美しいと思う。
金蔵寺の石垣。
仁王門。
境内のしだれ桜。まだ花が残っています。このあたりは自然環境保全地域になっているので、さまざまな広葉樹が借景となっています。
鐘をつく奥さん。
本堂。応仁の乱の際に焼失したのを江戸時代の5代将軍綱吉の母、桂晶院が再建したのが今のお堂です。
境内から歩いてすぐのところにある見晴らし台。ここはハズせない場所です。
京都洛中を抱く比叡山と東山三十六峰が一望に見渡せます。ちなみに金蔵寺も比叡山延暦寺と同じ天台宗。
本堂からさらに少し登ると、愛宕大権現である勝軍地蔵が祀られている本殿があります。
勝軍地蔵は、神仏習合の際にイザナミが地蔵になったものですが、廃仏毀釈で勝軍地蔵が愛宕山から金蔵寺に移されると、愛宕山は、火の神カグツチを主神として祀るようになりました。
ちなみに、カヅツチは、イザナミが産んだ神ですが出産の際に大火傷を負ってイザナミは死んでしまいます。
なんだか、もう訳が分かりません。
金蔵寺をお参りした後はいよいよ小塩山頂上へ向かいます。
鮮やかな色のミツバツツジ。三枚の葉っぱが出ているのが特徴です。
小塩山頂上は、淳和天皇陵も兼ねています。淳和天皇は平安京遷都を行った桓武天皇から3代目の天皇で、十年程の在位の後、亡くなると遺言に従ってこの大原野の地に散骨されました。
天皇陵の脇に遠慮がちにある頂上の標識。642mなのでポンポン山(679m)より少し低い。
小塩山頂上からの道にカタクリの群生地区が3カ所あります。淳和天皇陵に一番近い場所が「御陵の谷」、NTT電波塔そばの「Nの谷」、炭焼き場跡のある「炭の谷」です。
それぞれ谷を下って行ったところにカタクリが咲いているので、3カ所全部周るとしんどいので、今回は、御陵の谷とNの谷の二か所に行きましたが、Nの谷のほうが多く群生していました。
カタクリは温度が上がると花を咲かせるのですが、今日は快晴ではなく風も吹いていたので、昨年ほどには咲いていませんでした。
本日のカタクリはほとんどが花を閉じて休憩モードでした。今の季節は毎日開閉を繰り返します。
一年に2カ月しか光合成をせず、8年かけてコツコツ貯めた養分で花を咲かせます。でもいったん成長すると40~50年生きるそうなので人間なみです。
8割がたが休憩モードでしたが、開花しているカタクリもいます。みんな下を向いているので写真を撮るのが難しい。
花咲かせようかどうしようか考え中💦
こちらは反り返るほど開花している陽気なカタクリ。
カタクリを楽しんだ後は下山します。大原野神社の駐車場へ向けての最短コースですが、雨水の水路と登山道が兼用なので、少し滑りやすく注意深く下って行きます。
沢が出てきたらほぼ下山終了。
登山道出口に出てきました。
広い棚田に出てきます。
先日も、ハナミズキ、コブシ、ハクモクレンの違いで悩みましたが、これは花びらが4枚なのでハナミズキ。 花びらの先に小さいアクセントがあります。
民家の石垣に群生しているシバザクラ。花が桜に似ています。
大原野神社駐車場前のお茶屋さんに咲いていたモクレン。
今日のしめくくりに草餅セットをいただきました。