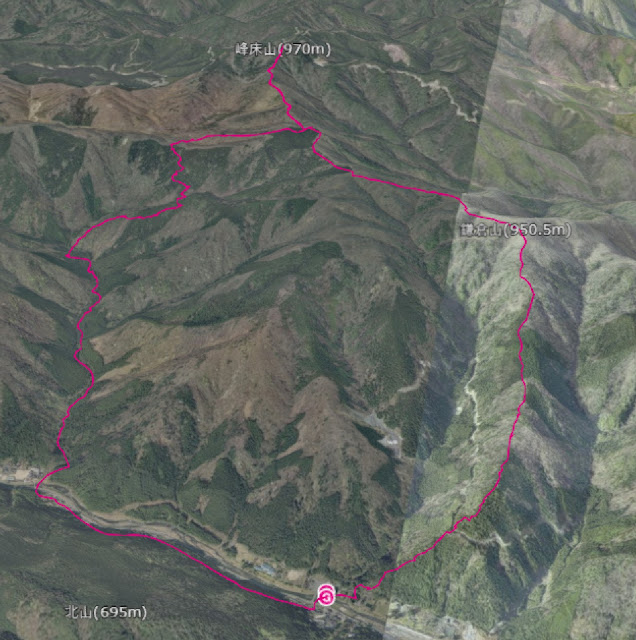朝9時前出発で、鴨川沿いを歩くと、光にきらめく川面に菜の花が色を添えます。
人が少ないので悠然としているアオサギ。ややこしいのですが、アオサギは頭が黒くて、くちばしが黄色。
中華料理屋さんのレトロな壁面が青空に映えます。
寺町通には、ハナミズキの花が咲いています。
ハナミズキは、北アメリカが原産で、日本がソメイヨシノをアメリカに贈った際に交換にもらったものだそうです。アメリカ人にとっては、ハナミズキを春の象徴としているようです。でも英語では Dogwood。なんで犬の花?
松原通りも、お店はすべて閉じており、閑散としています。おもてを掃除していたおばあさんが、「お店は閉まってますけど、清水寺は空いてますよ」と教えてくれました。
これは2017年に六波羅蜜寺と清水寺を訪れた時の写真です。今もしこんな状態になると、即座にクラスター発生です。
仁王門と三重塔。
清水寺の後ろにあるのは、清水山です。優しいお椀型の形が美しいです。
清水寺の山号は、音羽山。でも、音羽山というと大津の山を言うのが一般的ですが、清水山の別称も、音羽山なのです。ややこしいですね。
月の札の山は清水山ではないかと勝手に思っています。
平安京遷都以前から存在するお寺の数少ない一つですで、賢心という僧が夢のお告げで、清らかな水を求めてたどり着き、庵を結んだのが発端で、その後、賢心を訪ねた坂之上田村麻呂が建立し、その後、征夷大将軍となって蝦夷を征伐したという話になっています。
境内図です。今回もこのおススメルートで歩きます。
仁王門下の階段は、普段は、人混みのせいで撮影禁止なのですが、今日は特別。
随求堂(ずいぐどう)。
西門。西にある極楽浄土への入り口です。ここから、愛宕山が見えます。
アップしてみました。比叡山にゴツンとやられたというタンコブがわかります。
本堂は、何度も消失した後、江戸時代の初め、1633年に再建されたものです。
普段観光客で埋め尽くされている清水の舞台なのに誰もいません。マスクと手袋をしたスタッフが、お堂をしきりに雑巾がけしています。
いつも重さにチャレンジする錫杖も、今日はビニールでくるまれて、触れないようになっています。
江戸時代に本当に清水の舞台から飛び降りたのが235件で生存率85%だそうです。でもなんで飛び降りたのでしょうか。
清水寺ホームページより、ご本尊の十一面千手観音。オリジナルは焼失で、鎌倉時代の作だそうです。
拡大図。頭の上に、さらに二段の観音様が。一番上の観音様を千手の手が支えているのが面白い。
地主神社。お寺としての清水寺を守る役割である鎮守社(ちんじゅしゃ)。なぜか、縁結びの神様になっていて、普段は若い女子でいっぱいです。
色のコンビネーションがとても美しい今回のベストショットです。
屋根は四方に面のある寄棟造り(よせむねづくり)が、二面屋根の入母屋造り(いりもやづくり)の上に乗っかっている複雑な構造になっています。しかも、寄棟造りの端がカーブを描いています。表面はヒノキをつかった檜皮葺(ひわだぶき)。
檜皮葺は、2017年2月から3年がかりで葺き替えたものが、今回ようやく完了。新しい屋根で、ひときわ美しい。
139本のケヤキの柱で構築された日本を代表する懸けづくり。
愛宕山や西山を背景に京の街並みと一緒に。
ぐるりと回って下に降りていきます。
寺の名前の元となっている音羽の滝。
懸けづくりを下から眺めます。
石垣の草抜きの作業員の人たち。ロッククライマーなら、趣味と実益を兼ねられて、仕事が楽しいでしょうね。
鴨ものんびり。
八重桜。牡丹桜ともいいます。
観音様の変化仏の一つである如意輪観音をお祀りしています(写真はネットより)。
帰りは松原通りから、産寧坂を下ります。三年坂ともいう。
湯豆腐屋さんにしだれかかる枝垂桜。桜の花はないですが、新緑がまぶしい。
こんな、誰もいない産寧坂をもう見ることはないでしょう。というか、コロナ騒動のようなことは二度とゴメンです。
さて、牡丹を鑑賞するために西に歩いて建仁寺に来ました。
お茶の葉を、茶摘みの20日前頃から、日光を制限することで、渋み成分のカテキンに比べて甘味成分のテアニンが多く出ます。覆っていない周りにもお茶の木が、生垣として植わっています。
建仁寺の牡丹です。ベルベットのカクテルドレスのようなゴージャスさです。「百花の王」と言われるだけのことはあります。
この季節にしか見れない贅沢です。